|
1.フランスの運河の現状
(1)歴史的背景
ヨーロッパの中でフランスの運河を歴史的にみると、地形状分断されている大河川を結ぶ手段として、16世紀頃よりパリ、ダンケルクなど北東部を中心に発展してきた。しかし、現在、フランスの運河はすべて産業革命以前につくられた200から600トン程度の船しか通 れない小さな運河が殆どである。
ドイツ、オランダ、ベルギーなどが、将来の環境問題、化石燃料資源の有限性を見据えて、国境を越えた大型船の通 れる水路網として、運河網を整備、拡充しているのに対して、フランスの物流手段としての運河は一部は残るが、残りは歴史の彼方に消え去り行く運命にある。この点、歴史的にも、現在の置かれた状況からも、日本の河川舟運とよく似ているといえる。
しかし、国民がすぐれた水辺で遊べるように、レクリエーションのために、過去の歴史遺産をできる限りうまく利用する施策を採り続けており、その点について、国民のコンセンサスを得ているといえる。フランスの技術やシステムは、今後、日本が21世紀の舟運を考える上で参考になると考えられる。
(2)運河の利用者
最近の統計によれば、フランス全土で運河で生計を立てている船会社などの従業者は、わずか、3,214人、内訳はペニッシュ(船)を運航する零細自営業者1,229人、会社組織の乗組員1,554人、タグボート業者94人、管理職,技術者320人、レンタルボート会社94人(会社の数に比して従業員が少ないのは殆どがアルバイト)と内陸水運は凋落の一途の方向にあるといえる。
(3)運河の管理者
フランスの運河は、最近まで運輸省の国際航海局(ONN:Office National de la Navigation)が管理してきたが、1990年、機構改革によって、フランス水運公社(VNF Voies Navigable de France)が設立され、河川の公有地80,000haの管理権を与えられ、河川、運河の管理を独立採算を目標に行っている。
VNFは運輸省の補助を受け、ミディ運河、ローヌ・セート運河のような運河、ローヌ川、セーヌ川などの可航河川の維持、管理、補修を行い、運輸省は新規の運河建設、大規模改修を分担している(但し、パリ、マルセイユ、ダンケルクのような港湾は港湾管理者があり、ローヌ川には別 の開発公社がある)。
フランス全土で働くVNF職員の数は4,445人で、その内訳は閘門操作の職員3,901人、閘門の作業員は482人、季節だけ働く正規の操作員は62人である。運輸省時代にはもっと多くのロックキーパーが正規の職員としていたが、機構改革の時に、数千人解雇されたという。しかし、現在でも運河の維持管理に勤務している職員の数は船会社などの従業員数を上回っているのである。
VNFの予算は年間わずか12億フラン(264億円)で全土の運河の維持管理,整備を行っている。その内訳は維持補修に4億フラン、機械設備の更新に2億フラン、景観美化のために2億フラン、1995年にソーヌ川とライン川を結ぶ運河運河整備の借り入れ金の返済1.3億フラン、水資源管理1.1億フランである。それに対して収入は、運河税5.2億フラン、国からの補助金2.7億フラン、運河通 行税0.5億フラン(運河に登録されている船は通行税、運河税、公有地使用料を払う)、地方自治体からの補助金1億フランで毎年赤字経営が続いている状態である。
予算規模としては、建設省の一つの事務所程度の予算である。運河沿いのゴミの回収、水の供給はVNFの要請で自治体が協力している。運輸省とVNFの関係も未だきっちりしたものではないようである。ミディ運河の上流のあるこロックには、「国が補助金をくれないからVNFが単費でこのロックの改修を成し遂げた」という皮肉にも聞こえる看板を堂々と出していたところもフランスらしい。
![]()
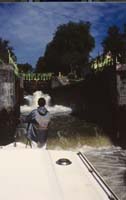 |
| ロックを上る醍醐味 |
2.歴史遺産としての運河
(1)栄光ある運河の歴史
フランスは15世紀より、歴代の為政者によってパリ、ダンケルクなど北西部、ローヌ川、ライン川を中心に数多くの運河をつくってきた。ルイ14世は世界初の大陸横断運河ミディ運河を、ナポレオンはパリ市内のサン・マルタン運河やパリと地中海とを結ぶためのブルゴーニュ運河など数多くの運河を手掛けるとともに、パリを中心とする現在のヨーロッパ国際運河網を提案し、ライン川など大河川の無差別 自由航行の原則を提案し、現在に至っている。
(2)歴史遺産としてのミディ運河
ミディ運河は、フランスを代表する運河で、フランス南西部ガロンヌ川の交易で栄えた町トゥルーズを起点として、カルカッソンヌを経て地中海に達する240kmに及ぶ世界初の大陸横断運河である。幅は16m〜19m、水深はおよそ2mとなっており、途中に存在する無数の閘門がノゥルーズの分水嶺を越えることを可能とした。
数多い閘門を昇降するスリル、美しい水辺を求めて、毎年多くの観光客がクルージングを行ない、隠れた観光名所になっている。クルージングは、数日間、フランス田園地帯の美しい風景を満喫し、巨大な水の圧力と格闘し、 古い港町に心誘われることによって、人の心を癒してくれる。
ヨーロッパの中でも歴史と伝統と格式ある運河のひとつであり、1997年にはユネスコの世界文化遺産に登録されている。フランスの運河整備の目的は、物流というより、歴史的遺産の復元、観光 資源の活用があるといえる。
|
|  <世界初の運河トンネルマルパトンネル> |
![]()
2.フランスの運河技術とソフトウエアー
(1)NFの維持管理思想
フランスもかっては、ドイツ、ベルギーと同じように、大きな水位差のリフト、インクライン、ペンテ・デ・アウ(水の楔)と呼ばれる装置をつくってきたが、VNFに管理移管された現在はない。
逼迫した事業予算で多くを維持管理することは難しく、交通量が多い場所に重点的に設備投資が行われているようである。ミディ運河では、ベジエーカルカッソンヌ間、ローヌ・セート運河では東のサン・ジルからフロンティニアンまでが整備され、交通 量が少ない運河のカルカッソンヌートウルーズ間では整備が遅れ、とくに、ローヌ・セート運河の西端のセート付近では土堰堤の護岸では崩れたまま放置されているところが多かった。航行に危険な
 |
| 水路幅一杯に航行するタンカー |
状態になると、水路の脇に木杭を打っている安全な航路幅を提供している
今回、航行中、偶然にもあるフランスでは珍しい事業に出会った。フロンティニアンの石油配分基地への輸送力増強を図っているのであろう、サンジルからフロンティニアンまではクラス4の1500トン級の船が航行できる水路に改良が進められている。この間、我々は2000トン近い大型のタンカーと舷々相摩すようにすれ違った。
南側の護岸は練り石積のコンクリート護岸に改良が加えつつあり、浚渫土を護岸脇に吹き上げている小型の浚渫船を見た。さらに、ボケールに近くでは、機械伐採を行っており、この付近の運河の維持管理はかなり省力化が進んでいることが、確認された。
このような近代工法を駆使して運河を改良している例は、ヨーロッパでも珍しいことであり、大変参考になった。
|
|  珍しい機械伐採の現場 |
(2)並木による環境と景観維持
ミディ運河のプラタナスの並木は400年前の建設当時に、リケの手によって植えられた。ミディ運河だけでなく、パリのサンマルタン運河、ウルク運河でも両岸には昔植えられた美しいプラタナスの並木が続いている。これがフランスの運河の空間デザインの技法の一つになっている。
|
|  美の極致、プラタナスの回廊 |
樹木が長い年月をかけて、成長し、我々に癒しと感動を与える水辺空間を形成するとともに、その根が護岸を強固なものにしている。
このプラタナスの護岸は、船を接岸する際の防舷材の役割も果たし、自然をうまく使うフランス人の合理的な考え方に感心させられる向きもあるが、これによって水路の維持管理費が掛からないということが挙げられよう。
(3)自治体が緑とゴミの処理
運河並木の剪定、緑の管理は、我が国同様、国(VNF)の要請で、管轄区域の自治体が行っており、このような自治体の下支えが歴史的遺産であるフランスの運河の存続を支えている。日本の河川管理制度と同じである。
(4)速度制限
我々のレンタル・ボートのみならず、運河を走る船は護岸を壊さないように、一般 に速度制限が設けられている(時速7ノットもしくは10km)。それ以上の速度であると、護岸を急速に壊すということが科学的に知られている。
日本では、荒川,中川などで護岸崩壊が緊急課題になっているが、今後、日本も速度を抑える方向に議論は進むであろう。距離が短い日本で急ぐ理由がないからである。
 |
| 崩壊個所を木杭で防護 |
(5)コンクリート、鉄を極力使わない護岸
画一的なコンクリート護岸ではなく、ある場所では頑丈な構造物を、また、不必要な場所では単なる木杭を打っただけの構造、単なる植栽で防ぐなど、多様、かつ合理的な整備をしているようである。これも財源が不足していることに起因している。
これだけで航跡波で壊れるのを防いでいるので参考になる。汽水の影響を受け、プラタナスなど高木の並木が無くなるセートローヌ運河やミディ運河の河口部では、湖からの波が進入し、被災しそうな個所だけ申し訳程度に石積みの護岸やコンクリートの護岸などが整備されているのもフランスらしい。
また、河川と平面交差する場所やロックには、しっかりした構造物がつくられている。必要なところにはしっかりしたコンクリートの施設が造られている。この辺の考えは学ぶべきであろう。
日本のように「開かずの水門」を見慣れた我々にとって、平常時は開けたままの状態となって船を通 している様はユニークで、発想を変えることによってこのような水門が存在し得ることに感動を覚えた。
しかし、このようなフランスの護岸や構造物整備の考え方が、ヨーロッパの運河整備の一般 的な考え方ではない。
ドイツやオランダ、ベルギーの大型船が通過する主要運河では、ある意味では日本同様力まかせにがっちりした矢板護岸、ブロック、テックスタイルを用いた水路、護岸を様式として取り入れている。
|
|  河川との平面交差の構造物 |
(6)漁業者の協力
漁業者が水路や港をきれいに使っているかそうでないかの違いがある。牡蛎養殖の竹ざおやかご、漁具が乱雑に放置されている日本光景はフランスの運河の漁港にはない。ローヌ・セート運河では、漁港であっても家の前を花で綺麗に飾っている。要するに皆で運河を護っているのである。
(7)循環系の水路
ローヌ・セート運河は、セートからグラン・モット付近まではローヌ川やその他の河川の河口デルタが形成するいくつもの沼沢地を貫くように走っているために、沼や湖の中を通 過するときには、両側に土手(土堰堤)を有する狭い一本の水路となっている。真珠のネックレスの個々の真珠が湖や沼とすれば、その紐が運河である。日本にはない珍しい水の風景である。
北側の土手には、ところどころ、湖沼との連絡水路がある。これは、運河と湖沼との水循環の役割を果 たしている。沼、湖などの湿地帯が臓器であるとすれば、血管のように外とを結び水循環を促す効果 もあると考えられる。
すなわち、湿地の水位が上がれば、これら小さな越流堤から湿地の中の水が運河を通 って外に排出される。反対に水位が低くなると、運河の水が湿地のほうに流れ出る仕組みになっている。ローヌ川からの水脈が動脈、この広大な湿地帯が肺、運河が静脈の役割を果 たしているといえる。
|
|  水の循環が生命に活力を与える |
北側の崩れた護岸の背後には湿地帯、中之島の草地、荒地といった異なる種類の環境が連続しており、そこには様々見られる。水路が両側の水辺環境を完全には分断していないことで、湿地から水路にかけて連続した環境が形成されている。中の島になっている部分は、小石が積もって河原のようになっていたり、背の低い草で覆われている。そこはカモメ、野ウサギのコロニーにはぴったりの場所となっている。
|
|  サイクリングとフラミンゴ |
また、右岸側の土手で草が生えておらず、土が露呈している断崖状になった場所には、カワセミであろう多くの巣穴があったし、潅木の茂みの下にはウサギ穴が数多く見られた。
日本では、一度にこんなに多くのカワセミや野うさぎを見たことがないので、はじめは眼を疑った。
護岸の背後には州や草地が出来ているが、護岸が連絡水路で分断され、人間が行けない孤立した地形になっているため、日本では同時に見ることのない野ウサギ、馬、水牛、フラミンゴなどたくさんの生物がパノラマのように現れ景色としては単調であるが、おもしろい環境だった。人間が縁を切ることによって沢山の生物が棲息できる環境ができるものだと実感した。
(5)ボランティアの活用
夏のバカンス・シーズンになると操作員は権利としての休暇を取り、その穴埋めはボランティアを大量 に雇うことになる。夏のミディ運河はボランティアにとって人気の場所、夏のバカンスの時期になると、かわいい女の子のボランティアが数多く働く。彼女らにとって、ロックキーパーは夏休みの楽しい息抜きのバカンスでもあるようだ。
|
| 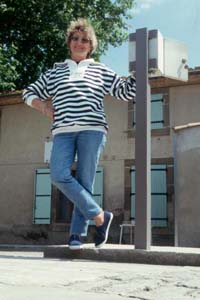 笑顔でバイバイ |
![]()
3.日本との比較 -手を加え方を美しく-
これら南仏の海岸に沿って走る二つの運河をつぶさに眺めるとき、貞山堀、新河岸川の課題を示唆することができる。
日本を代表する貞山堀は、北上運河、東名運河、そして岩沼付近が一部運河としての姿を止めているものの、総じて水深は汚泥がたまり浅く、仙台市の部分は農業排水路と化し、多賀城では仙台新港によって分断され、全体として運河としての機能は失っている。
一方、新河岸川においては、川越付近は美しいが、周辺からの下水、農業排水を集めて流れる単なる川に変貌し、一部でその名残りを止めているにすぎない。
これは運河の歴史の重みを忘れ、関係する歴史遺産を行政機関が分断し、自らの機能に変形、特化させて、管理しているために、ある部分は都市下水の排水路として、農業排水路として、河川として、港湾の一部として一貫性がない使われ方をしてきたのではないだろうか。
日仏の低湿地を貫く運河風景の違いの要因は、第一にフランスでは極めてルーズなあいまいな空間を水路周辺につくっているのに対し、日本の水辺空間は画一的、直線的である、技術もそうである。
すなわち、フランスでは自然にまかせ野生生物が育つよう海や運河と水田、耕作地の間に豊かな汽水域をつくって、その中を通 しているのに対し、日本では、水田稲作のために水門で海水と河川をきっちり分けているために、結果 としって、開かずの水門によって腐った水が、滞留して環境を悪化させている光景が目につく。上流を考える動脈志向と併せて下流を考える静脈志向がこれから大切ではないかと感じた次第である。
最後に今回のクルーズで感じたことは、川や運河をよくするには、人が中に入り全体を眺め、観察することが不可欠である。そのためには、多くの人が船を浮かべ、交流することが必要である。北上川では北上運河の入口に運河交流館を建設し、交流が緒についたばかりであるが、全国の河川にこのような機能を持つ施設が増えてゆくことを望みたい。
最後に本稿は、今回の南仏運河クルーズの参加者、長野正孝、山田福太郎、半澤実英、川村健弘、前田嘉章の五名の寄稿を長野の考え、思想で取り纏めたものである。






